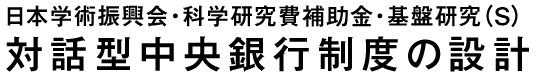-
„ÄĆśó•śú¨„Āģś†™ŚľŹŚłāŚ†ī„ÉĽŚāĶŚąłŚłāŚ†ī„Āę„Āä„ĀĎ„āčťáĎŤěćśĒŅÁ≠Ė„ĀģŚĹĪťüŅ„Äć
Abstract
śú¨ŤęĖśĖá„Āß„ĀĮ,śó•śú¨„Āę„Āä„ĀĎ„āčťáĎŤěćśĒŅÁ≠Ė„Āģś†™ŚľŹŚłāŚ†ī,ŚāĶŚąłŚłāŚ†ī„Āł„ĀģŚĹĪťüŅ„āíśėé„āČ„Āč„Āę„Āô„āčÁāļ„Āę,4„Ā§„ĀģŚąÜśěź„ā퍰ƄĀ£„Ā¶„ĀĄ„āč.1„Ā§Áõģ„ĀĮ,śó•śú¨„Āę„Āä„ĀĎ„ā蜆™ŚľŹŚŹéÁõäÁéá„āĄŚāĶŚąłŚŹéÁõäÁéá„Āęšļąśł¨ŚŹĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Āč„Ā©„ĀÜ„Āč„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀģŚąÜśěź„Āß„Āā„āč.ťĚíťáé(2008)„Āß„ĀĮ,ś†™ŚľŹŚłāŚ†ī„Āģ„ĀŅ„āíŚĮĺŤĪ°„Āę„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„ĀĆ,śú¨ŤęĖśĖá„Āß„ĀĮ,CampbellandAmmer(1993)„ĀģŚąÜśěźśČčś≥ē„ĀęŚÄ£„ĀĄ,ś†™ŚľŹŚłāŚ†ī„ĀęťĖĘťÄ£„Āô„ā茧Ȝēį„Ā®ŚāĶŚąłŚłāŚ†ī„ĀęťĖĘťÄ£„Āô„ā茏ƜĖĻ„ĀģŚ§Čśēį„ā팟ę„āÄVARšĹďÁ≥Ľ„ā팹©ÁĒ®„Āó,ś†™ŚľŹŚłāŚ†ī„Ā®ŚāĶŚąłŚłāŚ†ī„ā팹ܜ쟄Āó„Ā¶„ĀĄ„āč.„ĀĚ„ĀģÁĶźśěú„ÄĀś†™ŚľŹŚŹéÁõäÁéá„Āę„ĀĮ,ťĚíťáé(2008)„Ā®ŚźĆśßė„Āę,šļąśł¨ŚŹĮŤÉĹśÄß„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āô„āčšļč„āíÁĘļŤ™ć„Āô„āč„Ā®„Ā®„āā„Āę,ŚāĶŚąłŚŹéÁõäÁéá„Āę„āāšļąśł¨ŚŹĮŤÉĹśÄß„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āô„āčšļč„āíÁĘļŤ™ć„Āó„Āü„Äā2„Ā§Áõģ„ĀĮ,Kuttner(1996)„āĄBernankeandKuttner(2005)„Āߌą©ÁĒ®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč,ŚÖąÁČ©ťáĎŚą©„ā팹©ÁĒ®„Āó„Āü„ÄĆSurpriseŚ§Čśēį„ĀęŚĮĺŚŅú„Āô„ā茧Ȝēį„āí,śó•śú¨„Āģ„Éá„Éľ„āŅ„āíÁĒ®„ĀĄ„Ā¶šĹúśąź„Āó„Āüšłä„Āß„ĀģśôāÁ≥ĽŚąóŚąÜśěź„Āß„Āā„āč.śú¨ŤęĖśĖá„Āß„ĀĮ,śó•śú¨„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚÖąÁČ©ťáĎŚą©„Ā®„Āó„Ā¶,HondaandKuroki(2006)„Ā®ŚźĆśßė„Āę,„ÄĆŚÖąÁČ©„ɶ„Éľ„É≠ŚÜÜ3„É∂śúą„āā„Āģ„Äć„ā팹©ÁĒ®„Āó„Āü.„ĀĚ„ĀģÁĶźśěú,ś†™ŚľŹŚŹéÁõäÁéá„ÉĽŚāĶŚąłŚŹéÁõäÁéá„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶,„ÄĆSurprise„Ä挧Ȝēį„Ā†„ĀĎ„ĀĆśúČśĄŹ„Āꍙ¨śėéŤÉĹŚäõ„āíśĆĀ„Ā§šļč„ĀĆÁĘļŤ™ćŚáļśĚ•„Āü„Äā„Āď„ĀģÁĶźśěú„āą„āä,śú¨ŤęĖśĖá„ĀßšĹúśąź„Āó„ĀüťáĎŤěćśĒŅÁ≠ĖŚ§Čśēį„ĀĆ„ÄĆšļąśúü„Āē„āĆ„Ā™„ĀĄ„ÄćťáĎŤěćśĒŅÁ≠Ė„ĀģšĽ£śõŅŚ§Čśēį„Ā®„Āó„Ā¶,šłÄŚģöÁ®čŚļ¶śúČŚäĻ„Āęś©üŤÉĹ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®Śą§śĖ≠ŚáļśĚ•„āč„Äā3„Ā§Áõģ„ĀĮ,„ÄĆSurprise„Ä挧Ȝēį„āíÁĒ®„ĀĄ„Ā¶,ÁĒ£ś•≠Śą•„Āģś†™ŚľŹŚŹéÁõäÁéá„ĀęŚĮĺ„Āô„āčťáĎŤěćśĒŅÁ≠Ė„ĀģŚĹĪťüŅ„ā팹ܜ쟄Āó„Āü„Āď„ĀģÁĶźśěú„ÄĀ„ÄĆťĚěťČĄťáĎŚĪě„ÉĽś©üśĘį„ÉĽŚįŹŚ£≤ś•≠„Äć„Ā™„Ā©„Āģś•≠Á®ģ„Āß„ĀĮ„ÄĆSurpriselŚ§Čśēį„ĀĆśúČśĄŹ„Āꍙ¨śėéŤÉĹŚäõ„āíśĆĀ„Ā§„ĀĆ„ÄĀŚÖ¨ŚÖĪśÄß„Āģťęė„ĀĄ„ÄĆťõĽśįó„ÉĽ„ā¨„āĻ„Äć„āĄ„ÄĆśįīÁĒ£„ÉĽŤĺ≤śěóś•≠„Äć„Ā™„Ā©„ĀģÁ¨¨1ś¨°ÁĒ£ś•≠„ÄĀśĒŅŚļú„ĀģŤ¶ŹŚą∂„ĀĆŚľ∑„ĀĄ„ÄĆšŅĚťôļś•≠„Äć„ÉĽ„ÄĆÁ©ļťĀčś•≠„Äć„Ā™„Ā©„Āģś•≠Á®ģ„Āß„ĀĮ,„ÄĆSurprise„Ä挧Ȝēį„ĀĆśúČśĄŹ„Ā™Ť™¨śėéŤÉĹŚäõ„āíśĆĀ„Āü„Āö,ťáĎŤěćśĒŅÁ≠Ė„ĀģŚĹĪťüŅ„ā팏ó„ĀĎ„Āę„ĀŹ„ĀĄšļč„āíÁĘļŤ™ć„Āó„Āü„Äā„ÄĆ4„Ā§Áõģ„ĀĮ,„Āď„āĆ„Āĺ„Āß„ĀģŚąÜśěź„ā퍳Ź„Āĺ„Āą„Āüšłä„Āß,„āĘ„É°„É™„āę„Āß„ĀģBernankeandKuttner(2005)„Āę„Āä„ĀĎ„ā茹ܜ쟄ĀęŚÄ£„Ā£„Āü,„ÄĆSurprise„Ä挧Ȝēį„āíÁĒ®„ĀĄ„ĀüťáĎŤěćśĒŅÁ≠Ė„ĀęŚĮĺ„Āô„ā蜆™ŚľŹŚłāŚ†ī„Ā®ŚāĶŚąłŚłāŚ†ī„Āł„ĀģŚĹĪťüŅ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀģŚąÜśěź„Āß„Āā„āč„ÄāÁĶźśěú„ĀĮ,Áü≠śúü„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶,ťáĎŤěćśĒŅÁ≠Ė„ĀĆś†™ŚľŹŚłāŚ†ī„ĀęŚĹĪťüŅ„āíšłé„Āą„āč„āā„Āģ„Āģ,„ĀĚ„ĀģŚäĻśěú„ĀĮśłõŚįĎ„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹšļč„ĀĆÁĘļŤ™ć„Āē„āĆ„Āü„Äāś†™ŚľŹŚłāŚ†ī„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ÄĆCampbellŚě茹ܜē£ŚąÜŤß£„Äć„ĀģŚźĄŤ¶ĀŚõ†„ĀģŚŹćŚŅúšŅāśēį„āíÁĘļŤ™ć„Āô„āč„Ā®,ťÖćŚĹď„Ā®ŚģüŤ≥™Śą©Ś≠źÁéá„ĀģšŅāśēį„ĀĆś≠£„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ,šļąśúü„Āó„Ā™„ĀĄťáĎŤěćśĒŅÁ≠Ė„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶,ťÖćŚĹď„Ā®ŚģüŤ≥™Śą©Ś≠źÁéá„ĀĆś≠£„ĀģśĖĻŚźĎ„ĀꌏćŚŅú„Āô„āč„Āď„Ā®„āíťÄö„Āė„Ā¶ś†™ŚľŹŚŹéÁõäÁéá„ĀłŚĹĪťüŅ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„āíÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč.ťÖćŚĹď„ĀģŚŹćŚŅú„ĀĮ„āĘ„É°„É™„āę„Āę„Āä„ĀĎ„āčÁĶźśěú„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč.„Āď„Āģ„Āď„Ā®„Āč„āČ,„ā∑„Éß„ÉÉ„āĮ„ĀģŚĹĪťüŅ„Āģśļźś≥Č„ĀĆśó•śú¨„Ā®„āĘ„É°„É™„āę„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶Áēį„Ā™„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀƜ鮌Įü„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚāĶŚąłŚłāŚ†ī„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ÄĆCampbellŚě茹ܜē£ŚąÜŤß£„Äć„ĀģŚźĄŤ¶ĀŚõ†„ĀģŚŹćŚŅúšŅāśēį„āíÁĘļŤ™ć„Āô„āč„Ā®,ŚģüŤ≥™Śą©Ś≠źÁéá„Ā®„ā§„É≥„Éē„ɨÁéá„ĀģšŅāśēį„ĀĆ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ,šļąśúü„Āó„Ā™„ĀĄťáĎŤěćśĒŅÁ≠Ė„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶,ŚģüŤ≥™Śą©Ś≠źÁéá„Ā®„ā§„É≥„Éē„ɨÁéá„ĀĆś≠£„ĀģśĖĻŚźĎ„ĀꌏćŚŅú„Āô„āč„Āď„Ā®„āíťÄö„Āė„Ā¶ś†™ŚľŹŚŹéÁõäÁéá„ĀłŚĹĪťüŅ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„āíÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā
Introduction
ÁĶĆśłą„ĀģŚčēŚźĎ„āíśä䜏°„Āô„āčśúČŚäĻ„Ā™śČčśģĶ„ĀģšłÄ„Ā§„ĀĮ,ś†™ŚľŹŚłāŚ†ī„āĄŚāĶŚąłŚłāŚ†ī„Ā™„Ā©„ĀģŤ≥áÁĒ£ŚłāŚ†ī„ĀģŚčēŚźĎ„āíś≥®Ť¶Ė„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„Āā„āč.„Āĺ„Āü,ś†™šĺ°„ĀģŚ§ČŚčē„āĄŚāĶŚąłšĺ°ś†ľ„ĀģŚ§ČŚčē„Āę„ĀĮŚ§ö„ĀŹ„ĀģŤ¶ĀŚõ†„ĀĆŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„āč.„ĀĚ„Āģšł≠„ĀßÁČĻ„Āęťá捶Ā„Ā™Ť¶ĀŚõ†„Ā®„Āó„Ā¶,ś†™ŚľŹŚłāŚ†ī„Ā®ŚāĶŚąłŚłāŚ†ī„ĀĆšļí„ĀĄ„ĀęŚĹĪťüŅ„ā팏ä„Āľ„Āó„Āā„ĀÜŤ¶ĀŚõ†„āĄ,ÁĶĆśłąśĒŅÁ≠Ė„ĀęťĖĘťÄ£„Āô„ā荶ĀŚõ†„ĀĆśĆô„Āí„āČ„āĆ„āč„Äā